コラム

厚生労働省労働局長登録教習機関
北海道・宮城県・岩⼿県・福島県・東京都・⼤阪府・福岡県

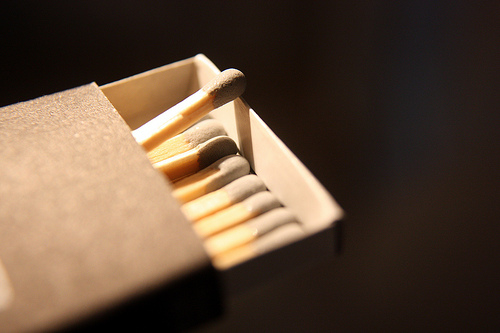
火災や爆発の危険がある引火物の取扱い時には、準備が必要です。
その準備は、引火させないよう火の気を遠ざけることと、気体が溜まらないようにすることです。
引火物であっても、燃え広がるにしても、一定の濃度が必要です。 濃度を薄めてやることは、火災の防止になるのです。
引火物取扱い時の環境づくりについても、安衛則では規定しています。
| 引火物取扱い時の通風、換気 |
【安衛則】
| (通風等による爆発又は火災の防止) 第261条 事業者は、引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は可燃性の粉じんが存在して爆発 又は火災が生ずるおそれのある場所については、当該蒸気、ガス又は粉じんによる爆発 又は火災を防止するため、通風、換気、除じん等の措置を講じなければならない。 |
引火物や可燃性ガスや粉じんを取り扱う場合は、火災や爆発を防ぐため、通風、換気、除じんを行います。
これは蒸気の濃度を薄めてやり、引火を防ぐのです。
火種があっても、燃えるものがなければ燃え広がりません。
風通しをよくすることは、引火物を取り扱う上で、非常に重要なのです。
| 通風、換気が不十分な場所での溶接作業の注意 |
ガス溶接は、酸素などのガスを噴出し高温の火で溶接するものです。 可燃性ガスを用いるので、換気などが重要です。
しかし、タンクや容器の中など、風が入らず、換気も充分でない場所で溶接しなければならないこともあります。 この時、最も注意しなければならない点は、ガス漏れです。 漏れたガスが、溶接の火で爆発というのが怖いのです。
通風や換気が充分でない場所での溶接作業では、ガス漏れによる爆発や火災を防がなければなりません。
漏れやすいポイントは、次の箇所です。
1.ホースや配管が破損、摩耗している箇所。
2.ホースの接続部。
これらのポイントは、よくよく点検します。
接続箇所は、確実に接続します。
溶接作業にあたっては、ガス等が放出しない状態にした吹管や栓をしてから、作業します。
ガスの容器を作業している人以外の人が、勝手に操作すると危ないですよね。知らないうちに、大量のガスが送り込まれていたら、溶接している人にとっては、恐怖です。
そのため、取扱う人の名札を容器やガスコックに取付けて、第三者が操作できないようにします。
酸素が過剰に出て火傷しないために、溶接作業中は十分な換気を行います。換気は送風機などを使います。
もし溶接作業の途中で、その場を離れる時は、ガスの供給を止めるために、ホースや容器を風通しの良い場所に置きます。ホースを置くのは、内部のガスを拡散するためです。
ガスが漏れないようにすること、作業場にたまらないようにすることが、重要と言えます。
| ガス等の容器の取り扱いの注意 |
ガスを保管している容器は、取り扱い方を間違えると、大爆発しかねません。 ガス漏れはもちろんのこと、保管の仕方自体も注意が必要です。
ガス容器の保管は、適切に行わなければなりません。
注意点が、各号でまとめられています。
1.通風が悪い、近くに火気がある、火薬や爆発物の近くには保管しない。
2.温度は40度以下にする。
3.転倒の恐れのない場所に置く。
4.衝撃を与えない。
5.運搬時は、キャップする。
6.バルブ開閉は静かに行なう。
7.溶接アセチレンガスは立てて置く。寝かせない。
8.使用前と使用後の容器の区別をはっきりさせておく。
どれも当たり前のように思うのではないでしょうか。
当たり前のようですが、基本的なことなので、保管に際しては、十分に注意します。
ガス溶接は、可燃物のすぐ側で火を扱います。
制御できている間はよいのですが、意図せず漏れだしたガスに引火すると非常に危険です。
ガスの保管や取扱いは、注意が必要ですね。
まとめ。
【安衛則】
| 第261条 引火性の物の蒸気等で、爆発又は火災が生ずるおそれのある場所では、火災対策をしなければならない。 |
| 第262条 通風又は換気が不十分な場所において、可燃性ガス及び酸素を用いて溶接等の作業を行なうときは、火災等の対策をしなけれならない。 |
| 第263条 溶接等に使用するガス等の容器は十分に取扱に注意しなければならない。 |
